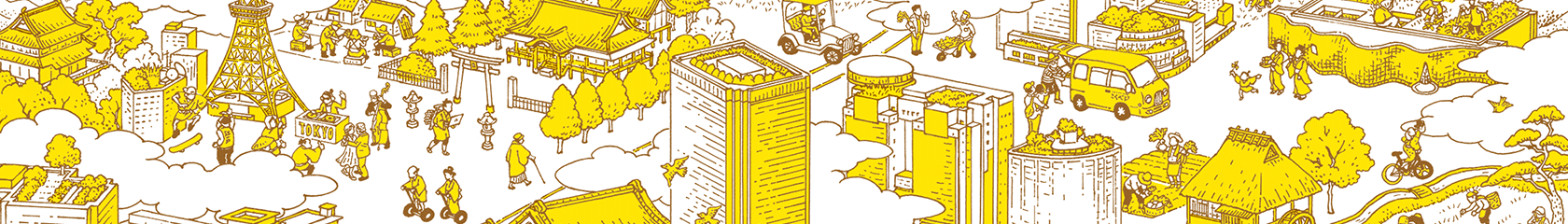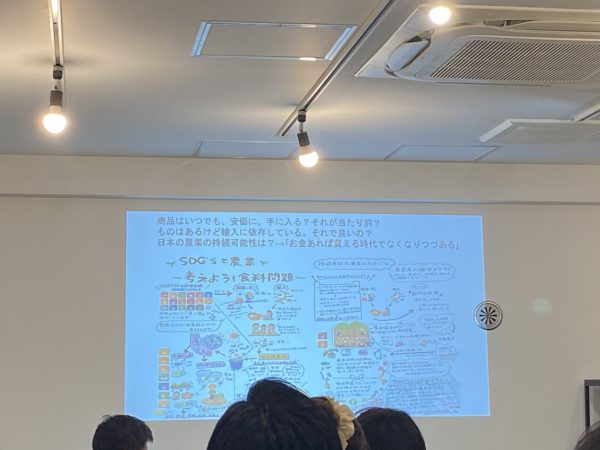これ誰のトマト?東京産のトマトを食べ比べ![農家と食べようin東京農村 イベント開催レポート]
東京農業の発信施設「東京農村」(赤坂見附)にて、6月16日に一般の方を対象にしたイベントである、
「これ、だれのトマト?東京トマト食べ比べ!5軒のトマト大集合!」~農家と食べようin東京農村~が開催されました。
トマトを食べることが大好きな方がトマトの食べ比べを通して、「どんな品種やどんな工夫だと、どんな味になるのか?」をじっくりと感じていただき、
さらに東京・府中市で、美味しいトマト作りに励む新進気鋭の農家・小勝正太郎さんをお招きして、トマトの栽培についてお話を聞き、トマトに対する理解をさらに深める時間となりました。
トマトの食べ比べでは、東京でトマトを生産している5名のトマト(桃太郎、桃太郎プレミアム、麗夏、りんか409、サンロード)を使用させていだだき、品種や栽培方法によってどのような味の変化があるのかを楽しんでいただきました。
参加者の皆さんはトマトを日頃からたくさん食べていますが、それでも味の違いを判断するのは難しく、美味しいと言いながらも首を傾げながら食べている光景はとても印象的でした。
その後は小勝さんにトマト栽培についてお話をしていただきました。
小勝さんの栽培するトマトの美味しさの秘訣、トマト栽培の技術的なハードルや、農薬と光合成の工夫についてお話をしていただき、その中でも光合成の研究と体にやさしい農薬の紹介が印象に残りました。
ハウスには光合成を効率よく行うための環境制御装置がついており、湿度が下がると小勝さんの所持している携帯に警報メールが入る仕組みになっているそうです。
また、農薬においても食用ヤシ油や、納豆菌の仲間など、人間が食べれる材料で作られているものを使用しており、一概に農薬は悪であるという考えではなく、工夫しながら農薬と上手く付き合っていくという考えにとても感心しました。
最後は、旬の素材が自慢のイタリアンバル『東京野菜キッチン SCOP』の星野允人さんが東京都産のトマトを使用した料理を囲みながら、小勝さんと交流を深める座談会を行いました。農家さんと消費者である参加者の方々が実際に交流を深める機会はあまりないため、とても貴重な時間となりました。
東京産のトマトを実際に生産している農家さんの前で食べ比べすること、栽培方法を農家さん自身から説明していただくこと、そしてその農家さんと実際にお話をしながら料理を食べること、このイベントの全てが新しく、とても貴重な時間になりました。
今回の反省も踏まえて、是非第二回も開催させていただきたいと思っております。
協力していただいた生産者の方々、そして参加していただいた皆様、誠にありがとうございました。
エマリコくにたちインターン生 秋草 楠