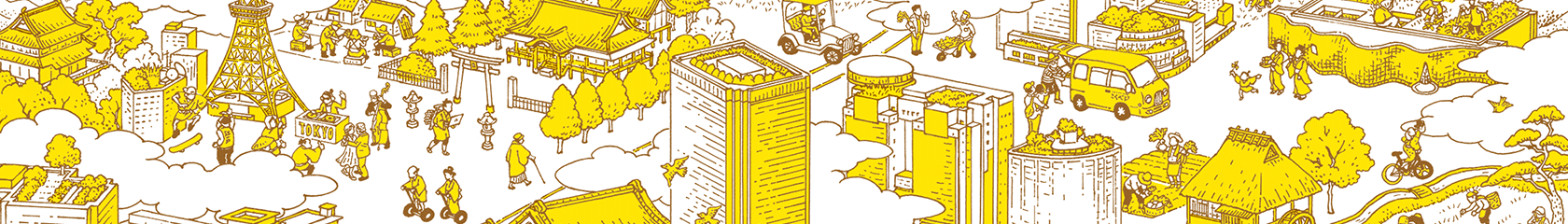【東京農サロンNEO】2026年11月 徳川将軍献上「奥多摩わさび」存続の危機にたちむかう!レポート
11月19日、東京農サロンNEOが開催されました!
今回は奥多摩町町議会議員の伊藤英人さんと奥多摩町で観光業を営まれている角井仁さんにお越しいただき、奥多摩町のわさび栽培の現状とわさびを使った地域おこしの取り組みについてお話いただきました。
奥多摩町は町全域が国立公園に指定されていて、標高は最高点で2000mを越えるほど。
森林に囲まれた高地であり、寒冷な気候を生かして伝統的にわさび栽培が営まれてきました。
その歴史は江戸時代にさかのぼり明確な記録はないものの、1823年に描かれた武蔵名勝図絵には幕府に献上していた記録が残っているそうです。
わさび栽培は奥多摩町の主要産業である林業と作業に親和性があり、山の管理の一環として林業に次ぐ第二の収入源として、副業のような形で実施されてきたのだといいます。
伊藤さんも町議会議員としてご活躍されると同時に、今から15年ほど前にわさび栽培を一から習得し、今ではご自身のわさび田を所有されています。
奥多摩町では、わさび生産者が高齢化していて、生産量も微増減を繰り返しながらも過去最低を記録する中で、町として後継者を育成する取り組みが実施されています。
その名も「わさび塾」。わさび塾では2年間でわさび栽培の手法を一から習得できるそうで、現在まで18期続き、計約100名ほどが修了しています。町がわさび栽培の存続を支援する仕組みが存在しています。
伊藤さんの言葉の節々からは町議会議員として奥多摩のわさび栽培文化を守り抜いていく責務のようなものを感じました。
もう一人のゲスト、角井さんは、”現代型副業”わさび生産者です。
角井さんは奥多摩町の出身ではなく、ご自身の趣味であったキャニオリングという渓谷を舞台にするアウトドアスポーツを通じて奥多摩町に出会い、その自然に魅了され奥多摩町に移住されたといいます。
角井さんは奥多摩町で観光業を営んでいて、キャニオニングを主催していらっしゃいます。ですがキャニオニングは夏のスポーツなので、冬は寒い時期に収穫を迎えるわさびを中心にしたツアーを開催されているそうです。
角井さんは観光業の副業としてわさび栽培を行うと同時に、わさびを奥多摩の観光資源に組み込もうと尽力されている方です。
わさびツアーでは、わさび田に実際に訪れて最後には名物のわさび丼を食べることができ、近年では海外からの観光客も増えているそう。奥多摩が大規模生産地とは異なり、渓流の地形を生かしてわさび栽培をしているからこそ成り立つツアーですね。
また角井さんはツーリズムの一部でバーベキュー場を運営する中で、わさびのおいしい食べ方を提案するほか、わさび食堂を運営して奥多摩産のわさびをより多くの人に届けていらっしゃいます。
生わさびを加工品にするのではなく、奥多摩町に来てもらって食べてもらう。奥多摩町に移住を決める程魅力を感じている角井さんからは、奥多摩の魅力を作りたい、伝えたいという強い思いを感じました。
お二人とも貴重なお話ありがとうございました!
エマリコくにたちインターン 坂井陸斗