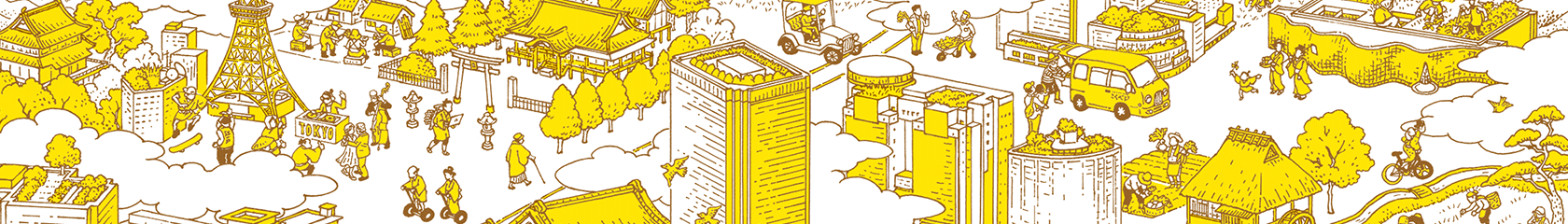6月の東京農サロンは、7周年記念のスペシャル回!!
通算78回目となる今回は、東京大学空間情報科学研究センター・准教授の新保奈穂美さん、千葉商科大学人間社会学部・准教授の小口広太さんをお招きし、アカデミアの視点から見た都市農業について熱いお話を伺いました。
1人目のゲストスピーカー 新保奈穂美さんは、以前『まちを変える都市型農園 コミュニティを育む空き地活用』を出版された際にも東京農村でお話しいただきました。今回も、国内外の事例を織り交ぜながら、都市を変革するツールとして発展してきた都市型農園の歴史や役割について伺いました。
都市の変革ツールとなる!? 都市農業の意義
都市型農園の歴史は遡ること19世紀ヨーロッパ。産業革命による都市の過密化で、感染症が蔓延する中、ドイツのシュレーバー博士が子どもたちの健康を促すため、緑の遊び場を作ったのが市民農園の発端と言われています。「クラインガルテン」と呼ばれる農地の貸借制度は、都市住民の小さな畑として親しまれています。また、2度の世界大戦中は食糧確保目的で都市型農地が各地域に広がりました。
日本においても、農業以外の土地活用を求めた農家と農に触れたい市民、双方のニーズによって、市民農園やコミュニティ農園などが徐々に広まってきました。特に最近はコロナ禍の貸農園ブームで、農を取り入れた暮らしが着目されてきています。
このような歴史からも分かるように都市型農園の機能は生産だけではありません。多世代にとっての居場所であり、防災・減災のための場所でもあり、環境教育、健康維持、資源循環など、、、幅広い価値を提供できる場所なのです。多様な意義がある一方で、関わる主体も農家、企業、市民、行政など多様化しています。そのため、イニシアティブをとっていく中間支援組織がないことが課題だと新保先生は指摘されていました。どのように都市型農園を活用し、よりよい都市空間を作っていくのか更なる議論を進めていかなくてはなりません。
ーーー
2人目のゲストスピーカー 小口広太さんは、日本農業経営大学校でも講師を務められた経験があり、鋭い視点で都市農業が抱える課題や今後の可能性についてお話しいただきました。
都市農業から生み出す!『畑を耕す市民』
近年浸透してきた「地産地消」という言葉。農産物と市民の物理的な距離は縮まってきましたが、農家と市民の人間的な距離は未だ離れたままだと小口さんは指摘します。さらに一歩先、農家と市民が協働する関係性を作っていくために小口さんが挙げていたのが「畑を耕す市民」です。現在は、市民農園や援農ボランティアなど様々な農業への関わり方が広がっています。とはいえ、経済的・時間的制約により、関わりたくても関われない人、もっと本格的に農業をやりたいのに余暇活動程度しか参加できない人など、ニーズのミスマッチは発生しています。そのため、農業との多様な接点を作り、階段状に様々な受け皿を準備していくことが必要となるのです。私たち市民自らが「畑を耕す市民」となり、農地をコモンズとしてみんなで守っていく関わり方が求められています。
老若男女問わず多様な人々を受け入れる包容力が都市農業の特徴です。そこにあるというだけで非常に価値がある、特異な存在です。だからこそ、生産性のものさしで図るだけでなく、多面的なものさしをもって都市農業の価値を見ていくことが重要となっていきます。今後は都市農業が、日本の農村社会の課題を解決するモデルになっていくだろうと小口さんは仰っていました。
お二方の都市農業に対する熱い思いに触れ、その後の懇親会も大盛り上がり。これからの都市農業に想いを馳せながら、熱い夜を過ごすことができました!